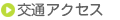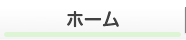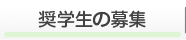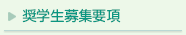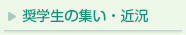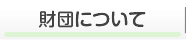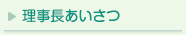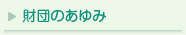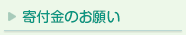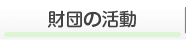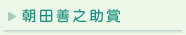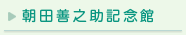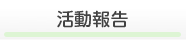2024年度「朝田善之助賞」の募集は個人及び団体(グループ)から2件の交付申請が提出されました。3月12日理事会において助成対象者を以下の通り決定しました。名前、研究テーマを研究目的・概要を掲載します。
1.淀野 実 さん
「人権」の地域づくりから「他文化共生」の社会づくりへ
前稿では、京都市立芸術大学の崇仁移転効果を東九条に波及させることによって、共に差別を乗り越え、全ての違いを認め合い、共に生きる「他文化共生」社会につなげていく「人権の地域づくり」の可能性について述べた。
様々な交流が深まるなど、大きな変化をもたらせ、両地区において芸術文化による地域づくりや、結合的なエスニック関係構築の土壌は出来つつあること。地域における人と人の関係の変革、更にアライを増やすことでマジョリテイを変えていくという
方向性は確認できたが、実現化に向けた道筋など、幾つかの課題が明らかになった。
両側からの歩み寄りがない中で、「理解し合える関係性をどう作っていくか」が、
本稿に課せられたリサーチクエスチョンである。
このため、本稿では京都市の新たな人権政策として、「誰一人取り残さない」福祉政策への転換を提唱する。そして、「崇仁・東九条の『両側から超える』を超える人権の地域づくり」を、更に「他文化共生の社会づくり」にまで昇華させていくための道筋や条件等についての検証を行う。
具体的には、目指すべき姿、将来像を「地域共生社会」+「多文化共生」と設定し、「誰一人取り残さない福祉社会」の具体像を描くとともに、SDGsや文化芸術、コミュニティオーガナイジング、ソーシャルデザイン等の実現手法について述べる。
次に、「他文化共生」という人権尊重の理念について、住民の総意として、立場や活動領域を越えた「共通言語」となるため、概念のブラッシュアップ等を図っていく。また、単なる「よそ者」から地域再生主体を形成し、創発的課題解決の役割を担う「関係者人口」に進化させていくこと、アライの概念を性の多様性から普遍的な人権問題へと拡大させ、更にアライを増やしていく手法等の課題について検討を加える。更に、楽只地区等、幾つかの先行事例の分析を通し、崇仁・東九条における今後のまちづくりの具体的実践につなげていく。最後に、「他文化共生」の社会づくりの実現可能性の追求や、新たな人権政策として、総合行政のあり方等について述べたいと考えている。
2.研究グループ有志 代表 小山 和夫さん
朝田善之助氏の部落解放理論発展史(戦前編・戦後編)
2022(令和4)年3月3日、全国水平社創立100周年を迎えた記念集会で、「部落解放同盟―新たなる決意―」が発表され、全国水平社の闘いを総括し、今後の組織と運動のあり様が示された。
50年前の全国水平社50周年記念を思い返してみると、第26回大会の運動方針は「水平社以来の50年の部落解放運動の発展過程にこそ、我々は、その運動を支え、発展させた力を見出さねばならない」とし、「水平社創立50年の歴史と伝統から学ぼう」と、「運動を支え、発展させた力」が何であったかを明らかにしたものであった。
当時の朝田善之助部落解放同盟中央執行委員長は「全国水平社50年の意義」と題する記念講演で、「部落解放運動の歴史と伝統」について、熱く語った。
解放運動の歴史とは、一つ一つの闘争をつねに運動発展の契機として、その経験を概括し、次への発展へと結びつける活動のみが継承されてきた歴史であり、闘いの中でわれわれを圧迫し苦しめている根源である差別は何かをつきとめ、どうしたら解放されるのかを明らかにしてきた過程であり、人々の主観を超え、つねにその「差別のとらえ方」に規定されてきたこと。
運動の伝統とは、闘争の歴史の中で培われてきた差別を客観的に明らかにしてきた理論であり、その理論に導かれた闘争形態を内容とするものである、と。
本論は、朝田氏が解放運動50年で明らかにした「差別とは何か」という「差別のとらえ方」が、「闘争形態」をいかに規定(反映)するかという解放理論の発展過程を、主な全国大会運動方針書及び主要な闘争の概括を通して明らかにした「解放理論発展史」である。朝田氏が生前に書き留めた書をもとに、指導を受け、編集、作成したものである。概括の仕方と朝田氏の姿勢は、部落解放運動のみならず、あらゆる社会運動の基本を示しているといえよう。
尚、内容が多いため、1年目は戦前編などと、2年にわたるかもしれない。
なお、助成対象者は2025年11月末までに研究成果をまとめ、研究報告書を提出していただきます。提出していただいた研究報告書を「朝田善之助賞」を2026年3月に決定し、発表いたします。「朝田善之助賞」受賞者は、2026年7月開催予定の研究報告会にて表彰いたします。