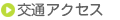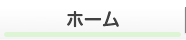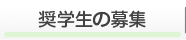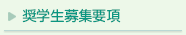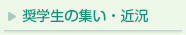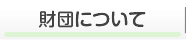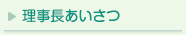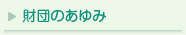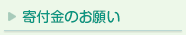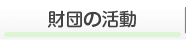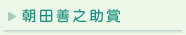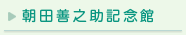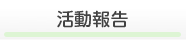「故郷に住み続けたい」という人権的な願いが差別的に扱われている
1.授業・研究、クラブ活動、ボランティア活動など
博士後期課程は2年目の後半に差し掛かるが、研究は順調に進んでおり、より高い質で仕上げられるよう日々邁進している。
博士研究は昨年から継続して「令和6年度能登半島地震後の公立小中学校の移動およびその課題」に着目した研究を進めている。研究と並行して、所属している「農村計画学会」内の災害対応委員会では、能登半島地震後の約1年半にわたり、石川県輪島市南志見地区に入り、住民懇談会の開催をはじめとした復興支援を行っている。現地調査において、地震発生から1年以上が経過してもなお、豪雨による壊滅的な被害の傷跡が残っていることが明らかとなった。被災地の復旧・復興には多大な時間がかかることを実感させられた。
能登半島地震後、被害の甚大な能登6市町では15の小中学校が自校舎を使用できない状態となったが、現在も被災規模の小さい近隣の他校に「間借り」している学校や、仮設校舎で新たな生活をスタートしている学校がある。この状況の中、市全体の被災による人口流出が止まらず、地区内すべての公立小学校の統合が進められている。本来、丁寧に進めるべき統廃合が災害を契機に急速に進んでいる現状がある。
このような状況を踏まえ、完全復旧までの学校移動の実態と経過を把握し、「学校という場所が複数回移動する」ことに対する子どもたちや学校関係者への負担、能登半島地震ならではの課題等について査読論文を執筆中である。また、市町全体の復興計画と学校復興の在り方についても継続して調査・研究している。
学校環境の変化により、発達障害等をはじめとした支援が必要な児童生徒に多大な負担がかかっているとの声も聴いている。統廃合には複式学級の解消等、多くの魅力がある一方で、小規模校として地域の中に公立小学校があることで、さまざまな児童生徒の受け皿になる可能性についても言及していきたいと考えている。
今後、今回の震災に匹敵する災害が発生した際に、学校再開への指標となることを願い、残り約1年の学生生活で博士論文として形にしていきたいと考えている。
2.「奨学生の集い・学習会」への期待・要望など
次回以降の「奨学生の集い・学習会」では部落差別に関する学習だけでなく、財団を通じて様々な大学・学部・学科に通う奨学生に対し、社会人ドクターという特殊な立場から今後の進路についてアドバイス等できればと考える。
3.差別・人権
能登半島地震後の奥能登地域をみると、「地震をきっかけに30年分の時間が一気に進んでしまった」という感覚を抱かざるを得ない。緩やかに進むはずだった過疎化が震災を契機に急速に加速し、地域コミュニティが将来的に継続できないのではないかという深い不安が広がっている。
その一方で、行政のアンケートや復興計画には、暗に集落の集約化を推し進める意図が見え隠れしており「住民の集落に住み続ける選択肢が奪われているのではないか」という感覚を持つようになった。こうした状況は、復興の過程において住民が置き去りにされ、情報共有や意思決定の参加機会が十分に保障されていないことを示している。
震災という非常事態がもたらした時間の急激な進行と、行政の方針の不透明さによって、住民は精神的な疎外感や不公平感に直面し、結果として「故郷に住み続けたい」という人権的な願いが差別的に扱われていることに気づかされた。このような現実を踏まえ、住民の声を反映した復興を進めることが不可欠でありそのための外部からの伴走支援が重要である。そうした取り組みこそが、持続可能な地域社会の再生と人権尊重の復興につながるのだと強く感じる。
大学院 博士後期課程 2年生 H.M.さん